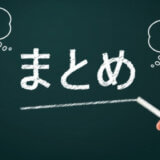この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
次の文を読み51、52の問いに答えよ。
Aちゃん(1歳7か月、女児)、在胎週数37週0日、出生体重1,980gで、低酸素性虚血性脳症でNICUに入院した。生後3か月に気管切開術を受け、24時間人工呼吸器管理である。他市からの転入のため保健センターに連絡があった。転入前に1歳6か月児健康診査は受診済みである。
市保健センターの保健師が家庭訪問をしたところ、父親(40歳)は単身赴任で、母親(38歳)がAちゃんの世話をしていた。Aちゃんは支えれば座ることはできるが寝返りは難しく、2時間ごとに気管内吸引と経管栄養を実施していた。外来診療(月1回)、訪問診療(月2回)、訪問看護(週1回)を利用し、身体障害者手帳1級(肢体不自由)は取得していた。市内に住む祖母(63歳)が手伝いに来ている。
51 Aちゃんの家族の健康課題をアセスメントするために、保健師が収集する情報で優先度が高いのはどれか。
1.祖母の育児負担状況
2.母親の心身の疲労状況
3.母親の訪問看護に対する満足度
4.単身赴任している父親の育児への思い
解答2
解説
・Aちゃん(1歳7か月、女児)
・在胎週数37週0日、出生体重1,980g、低酸素性虚血性脳症。
・生後3か月:気管切開術、24時間人工呼吸器管理。
・父親(40歳)は単身赴任、母親(38歳)がAちゃんの世話。
・Aちゃん:支えれば座ることはできるが寝返りは難しく、2時間ごとに気管内吸引と経管栄養を実施。
・外来診療(月1回)、訪問診療(月2回)、訪問看護(週1回)を利用。
・身体障害者手帳1級(肢体不自由):取得。
・市内に住む祖母(63歳)が手伝いに来ている。
→しっかり情報を読み込み、優先されるものを選べるようにしよう。
1.× 祖母の育児負担状況より優先されるものが他にある。なぜなら、祖母は、育児を手伝う立場にあるが、主たる介護者ではないため。祖母よりも主介護者である母親の健康状態を把握することがより緊急度が高い。
2.〇 正しい。母親の心身の疲労状況は、保健師が収集する情報で優先度が高い。なぜなら、母親は単身赴任中の父親に代わり、24時間人工呼吸器管理が必要なAちゃんの世話を中心的に担っているため。したがって、母親の心身の負担が非常に大きいと考えられる。
3.× 母親の訪問看護に対する満足度より優先されるものが他にある。なぜなら、設問文の情報収集する目的は「Aちゃんの家族の健康課題の評価」であるため。訪問看護への満足度は、サービス改善や継続のためには重要だが、現在直面している健康リスクに直接的に関係しにくい。したがって、まずは母親自身の健康状態を確認・支援することが優先される。
4.× 単身赴任している父親の育児への思いより優先されるものが他にある。なぜなら、単身赴任中の父親の育児に対する思いや意欲は、現在の直接的なケアに対する健康課題とはいえないため。したがって、父親が育児に強い思いを持っていても、物理的に離れているため、日常的な母親の負担軽減にはすぐには繋がらない。ただし、父親の育児への関与や思い、母親との関係性などは、長期的な家族支援体制を構築する上で重要な情報である。
次の文を読み51、52の問いに答えよ。
Aちゃん(1歳7か月、女児)、在胎週数37週0日、出生体重1,980gで、低酸素性虚血性脳症でNICUに入院した。生後3か月に気管切開術を受け、24時間人工呼吸器管理である。他市からの転入のため保健センターに連絡があった。転入前に1歳6か月児健康診査は受診済みである。
市保健センターの保健師が家庭訪問をしたところ、父親(40歳)は単身赴任で、母親(38歳)がAちゃんの世話をしていた。Aちゃんは支えれば座ることはできるが寝返りは難しく、2時間ごとに気管内吸引と経管栄養を実施していた。外来診療(月1回)、訪問診療(月2回)、訪問看護(週1回)を利用し、身体障害者手帳1級(肢体不自由)は取得していた。市内に住む祖母(63歳)が手伝いに来ている。
52 3か月後、母親から「新しい生活にAが慣れてきたので、Aが楽しめることを増やしてやりたい」と相談を受けた。
保健師の相談対応で優先度が高いのはどれか。
1.保健師の訪問回数を増やす。
2.発達相談支援事業所の通所を提案する。
3.祖母が児と遊ぶ時間をもてるよう調整する。
4.母に児との遊びを通したコミュニケーションを指導する。
5.訪問看護師に児とのコミュニケーションを増やせるか相談する。
解答2
解説
・Aちゃん(1歳7か月、女児、24時間人工呼吸器管理)
・父親(40歳)は単身赴任、母親(38歳)がAちゃんの世話。
・Aちゃん:支えれば座ることはできるが寝返りは難しく、2時間ごとに気管内吸引と経管栄養を実施。
・外来診療(月1回)、訪問診療(月2回)、訪問看護(週1回)を利用。
・身体障害者手帳1級(肢体不自由):取得。
・市内に住む祖母(63歳)が手伝いに来ている。
・3か月後、母親から「新しい生活にAが慣れてきたので、Aが楽しめることを増やしてやりたい」と相談を受けた。
→しっかり情報を読み込み、優先されるものを選べるようにしよう。
1.× 保健師の訪問回数を増やす優先度は低い。なぜなら、母「Aが楽しめることを増やしてやりたい」との相談であるため。単に、保健師の訪問頻度を増やすだけでは児の発達促進や楽しめる活動には直接つながりにくい。
2.〇 正しい。発達相談支援事業所の通所を提案する。なぜなら、発達相談支援事業所は、Aちゃんのような医療的ケアが必要な子どもや発達に課題のある子どもに対して、専門的な知識や経験に基づいた発達支援(遊びやリハビリテーションなど)を提供できる場所であるため。
3.× 祖母が児と遊ぶ時間をもてるよう調整する優先度は低い。なぜなら、「Aが楽しめることを増やしてやりたい」との相談であるため。医療的ケアが必要なAちゃんにとって、専門的視点を持っているものが、適切な環境での遊びを提供すべきである。
4.× 母に児との遊びを通したコミュニケーションを指導する優先度は低い。なぜなら、母はコミュニケーションに困っておらず、「Aが楽しめることを増やしてやりたい」との相談であるため。これは、児の社会参加や活動範囲の拡大を希望していると考えられる。
5.× 訪問看護師に児とのコミュニケーションを増やせるか相談する優先度は低い。なぜなら、母「Aが楽しめることを増やしてやりたい」との相談であるため。訪問看護師の役割は、健康管理や日常生活支援が中心である。母「Aが楽しめることを増やしてやりたい」という要望に直接応えることは難しい。
→訪問看護とは、看護を必要とする患者が在宅でも療養生活を送れるよう、かかりつけの医師の指示のもとに看護師や保健師などが訪問して看護を行うことである。訪問看護師の役割として、主治医が作成する訪問看護指示書に基づき、健康状態のチェックや療養指導、医療処置、身体介護などを行う。在宅看議の目的は、患者が住み慣れた地域で自分らしく安心して生活を送れるように、生活の質(QOL)向上を目指した看護を提供することである。療養者とその家族の価値観や生活歴を重視し、その人らしさやQOLを考える。
次の文を読み53、54の問いに答えよ。
A市で実施している1歳6か月児健康診査では、「経過観察」の割合が年々増加している。そこで、経過観察となった親子を対象に、県と連携して新規事業の立ち上げを検討することにした。
53 最初に取り組むのはどれか。
1.新規事業のプログラムの検討
2.事業の運営に携わるスタッフの選定
3.1歳6か月児健康診査で経過観察と判断した理由の分析
4.乳幼児を持つ母親への困りごとに関するアンケート調査の実施
解答3
解説
・A市で実施している1歳6か月児健康診査。
・課題:「経過観察」の割合が年々増加している。
・対象:経過観察となった親子。
・検討:県と連携して新規事業の立ち上げ。
→新規事業のステップを押さえておこう。ステップを飛ばしすぎると、的外れな事業となる恐れがあるため現状の分析は慎重に行う必要がある。
1.× 新規事業のプログラムの検討は時期尚早である。なぜなら、効果的なプログラムを作るためには、まず対象となる親子が具体的にどのような課題やニーズを抱えているのかを正確に把握する必要があるため。例えば、経過観察児の具体的な課題が明確になっていない段階でプログラムを作っても、的外れな事業となりやすく、効果が薄れてしまう可能性が高い。
2.× 事業の運営に携わるスタッフの選定は時期尚早である。なぜなら、どのようなスタッフが必要かは、事業の目的やプログラム内容が決まってからでないと判断できないため。必要な専門性(保育士、心理士、保健師など)や人数は、提供する支援によって変わる。
3.〇 正しい。1歳6か月児健康診査で経過観察と判断した理由の分析を最初に取り組む。なぜなら、今回の課題として、「経過観察」の割合が年々増加していることがあげられているため。したがって、まず、その原因を明確に特定し、実態を把握することが不可欠である。
4.× 乳幼児を持つ母親への困りごとに関するアンケート調査の実施より優先されるものが他にある。なぜなら、既存のデータ(健診結果)を分析し、「経過観察」と判断された理由という、より具体的で直接的な情報を把握することが先決であるため。つまり、母親の困りごと調査は、幅広いニーズ把握には役立つが、現在特定されている「経過観察児増加」の具体的な理由を特定することの方が先決である。
次の文を読み53、54の問いに答えよ。
A市で実施している1歳6か月児健康診査では、「経過観察」の割合が年々増加している。そこで、経過観察となった親子を対象に、県と連携して新規事業の立ち上げを検討することにした。
54 事業は母親が子どもと一緒に遊びながら関わり方を学んでいく内容で、月に1回、交通の便が良い会場で開催した。毎回、定員を超える希望者があった。県とは3か月に1回の連携会議を開催し、課題の共有と改善方法の検討を行った。1年後、参加者からは、子どもとの関わり方のヒントが得られ、安心して子育てができるようになったとの感想が聞かれた。
事業の評価の種類とその指標の組合せで正しいのはどれか。
1.プロセス評価:定員を超える希望者数
2.アウトカム評価:安心して子育てができると感じた参加者の増加
3.アウトプット評価:会場の交通の便の良さ
4.ストラクチャー評価:3か月に1回の県との連携会議の開催
解答2
解説
1.× 定員を超える希望者数は、「プロセス評価」ではなくアウトプット評価である。なぜなら、「希望者数」は事業そのものの成果(アウトプット)に近いため。
・プロセス評価とは、事業の手順や実施過程、活動状況の妥当性を評価するものである。例えば、事業参加者の募集方法、健康診査の従事者数・受診者数、事業の実施内容等が該当する。
2.〇 正しい。アウトカム評価:安心して子育てができると感じた参加者の増加
参加者が「子育てに安心感を持てるようになった」と感じる割合が増えれば、事業の目的(親子関係の改善、育児の安定化)を達成していることを示す。
・アウトカム評価(成果評価)とは、事業の目的を達成したかどうかの最終的な成果を判断するものである。例えば、参加者の6か月後のBMI値、糖尿病の治療継続者の割合、腹囲の減少率、参加者の運動回数などが該当する。
3.× 会場の交通の便の良さは、「アウトプット評価」ではなくストラクチャー評価である。なぜなら、「会場の交通の便の良さ」は事業の前提条件や環境要因(ストラクチャー)であるため。
・アウトプット評価とは、事業実施過程と参加状況などから直接生じた結果(数や量)を評価するものである。
4.× 3か月に1回の県との連携会議の開催は、「ストラクチャー評価」ではなくプロセス評価である。なぜなら、「3か月に1回の連携会議」は、事業運営過程(プロセス)に該当するため。
①ストラクチャー評価(企画評価):事業を実施するための仕組みや体制を評価するもの。
例:マンパワー、予算、会場の状況、関係機関との連携体制 等。
②プロセス評価(実施評価):事業の手順や実施過程、活動状況の妥当性を評価するもの。
例:事業参加者の募集方法、健康診査の従事者数・受診者数,事業の実施内容等。
③アウトプット評価:事業実施過程と参加状況などから直接生じた結果(数や量)を評価するもの。
④アウトカム評価(成果評価):事業の目的を達成したかどうかの最終的な成果を判断するもの。
例:参加者の6か月後のBMI値、糖尿病の治療継続者の割合、腹囲の減少率、参加者の運動回数 等。
次の文を読み55の問いに答えよ。
人口250万人のA県。特定健康診査の受診率が35%、特定保健指導の実施率は隣県より低い。40~50歳代の肥満と高血圧者が増加している。また、30歳代の喫煙率も男性が40%、女性が20%と隣県より高い。県の方針として健康寿命の延伸と生活習慣病予防を掲げ、地域・職域連携推進に取り組むために地域・職域連携推進協議会を設けることにした。
55 初回の会議で取り上げる議題で適切なのはどれか。2つ選べ。
1.A県の勤労世代における健康課題
2.高血圧の就労者に向けた講演会の内容
3.小規模事業者の特定保健指導のあり方
4.健康経営認定事業所を増やすための取り組み
5.協議会に参加する組織で実施している健康増進事業
解答1・5
解説
・人口250万人のA県(特定健康診査の受診率:35%)。
・特定保健指導の実施率:隣県より低い。
・40~50歳代の肥満と高血圧者が増加している。
・30歳代の喫煙率も男性が40%、女性が20%と隣県より高い。
・県の方針:健康寿命の延伸と生活習慣病予防を掲げる。
・目標:地域・職域連携推進に取り組む。
・対応:地域・職域連携推進協議会を設ける。
→ほかの選択肢が消去できる理由も上げられるようにしよう。
1.〇 正しい。A県の勤労世代における健康課題は、初回の会議で取り上げる議題である。なぜなら、初回の会議ではまず現状把握が不可欠であるため。したがって、A県の勤労世代の具体的な健康課題を共有する。
2.× 高血圧の就労者に向けた講演会の内容は優先されない(時期尚早)。なぜなら、初回の会議では、まず全体像(課題の共有、目標設定、大まかな戦略)を議論すべきであるため。講演会のテーマや講師の選定などは、協議会の役割や方向性が決まった後の詳細検討事項である。
3.× 小規模事業者の特定保健指導のあり方は優先されない(時期尚早)。なぜなら、小規模事業者の特定保健指導は、具体的な施策レベルの課題であるため。初回の協議会で議論すべき内容としては細部に入りすぎている。
4.× 健康経営認定事業所を増やすための取り組みは優先されない(時期尚早)。なぜなら、初回の会議では、まず全体像(課題の共有、目標設定、大まかな戦略)を議論すべきであるため。健康経営認定事業所増加の施策は、後の段階の具体的行動計画として位置づけられる。
5.〇 正しい。協議会に参加する組織で実施している健康増進事業は、初回の会議で取り上げる議題である。なぜなら、初回の会議で、各参加組織が実際にどのような健康増進の取り組みを行っているかを共有することで、地域・職域連携を進める上での強みや課題を明確化できるため。連携の可能性や課題を明らかにでき、次の具体的取り組みに繋げられる。
 希望の解説ブログ
希望の解説ブログ