この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
36 健康危機管理に関する保健所の業務はどれか。2つ選べ。
1.食中毒発生時の調査
2.狂犬病発生時の厚生労働大臣への報告
3.感染症患者を診断した医師からの届け出の受付
4.保育所で乳児が突然死したときの届け出の受理
5.虐待が認定された介護老人福祉施設の指定の取り消し
解答1・3
解説
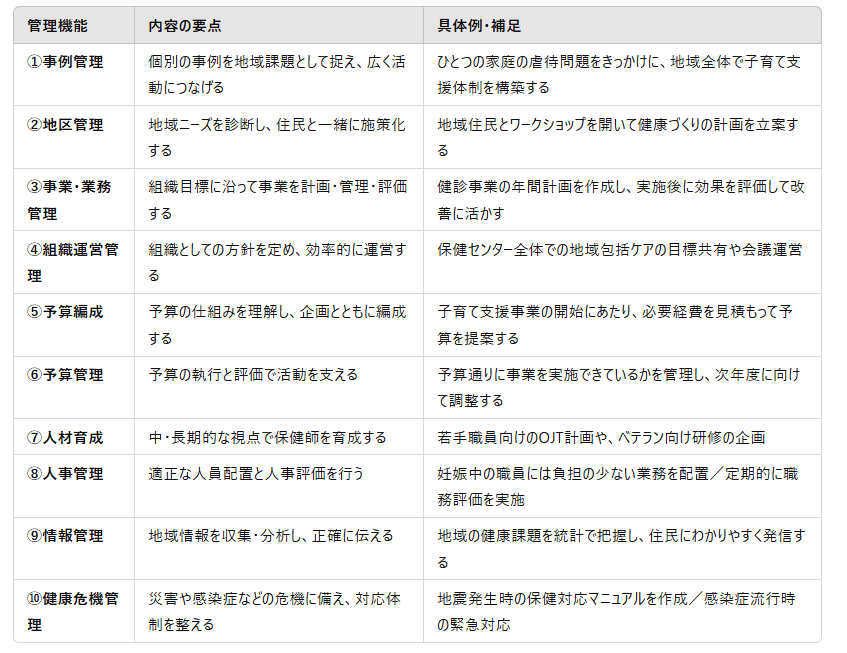
1.〇 正しい。食中毒発生時の調査は、健康危機管理に関する保健所の業務である。これは、食品衛生法63条2項「保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない」と記載されている(※引用:「食品衛生法」e-GOV法令検索様HPより)。
・食品衛生法とは、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための日本の法律である。所管官庁は、厚生労働省と消費者庁である。食品と添加物などの基準、表示、検査などの原則を定めている。
2.× 狂犬病発生時は、「厚生労働大臣」ではなく保険所長(のちに都道府県知事)への報告する必要がある。これは、狂犬病予防法8条1~2項において「狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかかつた疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出なければならない。ただし、獣医師の診断又は検案を受けない場合においては、その犬等の所有者がこれをしなければならない。2 保健所長は、前項の届出があつたときは、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。」と記載されている(※引用:「狂犬病予防法」e-GOV法令検索様HPより)。
3.〇 正しい。感染症患者を診断した医師からの届け出の受付は、健康危機管理に関する保健所の業務である。これは、感染症法12条において「医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない」と記載されている(※引用:「感染症法」e-GOV法令検索様HPより)。
4.× 保育所で乳児が突然死したときの届け出の受理は、市町村に行う。戸籍法第86~87条に基づいて「原則として死亡者の本籍地または届出人の所在地の市区町村長に提出・受理されること」と規定されている(※参考:「戸籍法」e-GOV法令検索様HPより)。
5.× 虐待が認定された介護老人福祉施設の指定の取り消しは、都道府県知事に行う。これは、介護保険法77条において「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる」と記載されている(※引用:「食品衛生法」e-GOV法令検索様HPより)。
厚生労働省は、平成6年に告示し平成12年に改正した「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」において、地方自治体が健康危機管理を適切に実施するための具体的な手引書を整備することを定めた。「地域健康危機管理ガイドライン」は、地方自治体がこの手引書を作成する際の参考となるように、地域における健康危機管理のあり方検討会がまとめたものである。
【健康危機管理の4つの側面】
保健所における健康危機管理の実際の業務は、対策の内容により、以下の4つの範疇に分けて整理することができる。すなわち、「健康危機の発生の未然防止」、「健康危機発生時に備えた準備」、「健康危機への対応」、「健康危機による被害の回復」であり、これらは健康危機管理業務の一連の流れとなる。
①健康危機発生の未然防止:管理基準の設定、監視業務等、健康危機の発生を未然に防止するための対策である。地域の状況を十分に把握し、保健所管轄区域において発生が予想される健康被害に応じた対策を講じることが重要である。
②健康危機発生時に備えた準備:健康危機がその時々の状況によって急速な進展をみることがあることから、保健所が迅速かつ効果的な対応を行うために、健康危機の発生に備えて事前に講じられる種々の対策である。これには、手引書の整備、健康危機発生時を想定した組織及び体制の確保、関係機関との連携の確保、人材の確保、訓練等による人材の資質の向上、施設、設備及び物資の確保、知見の集積等が含まれる。
③健康危機への対応:健康危機の発生時において、人的及び物的な被害の拡大を防止するために行う業務のことである。具体的には、対応体制の確定、情報の収集及び管理、被害者への保健医療サービスの提供の調整、防疫活動、住民に対する情報の提供等の被害の拡大防止のための普及啓発活動等のことである。また、被害発生地域以外からの救援を要請することも含まれる。
④健康危機による被害の回復:健康危機による被害の発生後に、住民の混乱している社会生活を健康危機発生前の状況に復旧させるための業務である。具体的には、飲料水、食品等の安全確認、被害者の心のケア等が含まれる。また、健康危機が沈静化した時点で、健康危機管理に関する事後評価を行うことも必要である。このとき、保健所による評価と、保健所の外部の専門家等による評価の双方を行うことが考えられる。実際に行われた管理又はその結果を分析及び評価することにより、管理基準の見直し、監視体制の改善等を実施し、被害が発生するリスクを減少させるための業務を行うことが可能となる。これらの評価を行うことにより、健康危機管理を行った組織等の健康危機管理の在り方についての見直しを行うことができる。さらに、健康危機管理の経過及びその評価結果を公表することにより、他の地域における健康危機管理のための重要な教訓ともなる。評価を行う際には、本ガイドラインにおける指摘事項を踏まえて評価することも考えられる。
(参考:「地域における健康危機管理について~地域健康危機管理ガイドライン~」厚生労働省HPより)
37 累積羅患率の計算に必要なのはどれか。2つ選べ。
1.観察開始時点での患者数
2.各観察対象者の観察期間の総和
3.観察期間に新たに発生した患者数
4.観察開始時点での観察対象集団の人数
5.観察終了時点での観察対象集団の人数
解答3・4
解説
累積羅患率とは、ある年齢までにある病気と診断されるおおよその確率である。ただし、その病気と診断されるまでは死なないという仮定のもとでの確率となる。①0〜64歳あるいは、②0〜74歳累積罹患率がよく用いられる。それぞれ①64歳までに、あるいは②74歳までにその病気と診断される確率の近似値として用いることができる。
【計算方法】
年齢階級別罹患率は、その階級に含まれる年数をかけたものを、特定の年齢まで足し合わせて求める。つまり、累積罹患率は、特定の期間中に新たに疾病が発生した人数を観察開始時点の集団の人数で割ったものである。
0〜74歳累積罹患率=0〜4歳年齢階級別罹患率 × 5年(0、1、2、3、4の5歳分が含まれるから)+5〜9歳年齢階級別罹患率 ×5年+…+70〜74歳年齢階級別罹患率×5年
(※参考:「累積罹患率」国立がん研究センターHPより)
1.× 観察開始時点での患者数は、主に有病率を算出するときに使用される。
・有病率とは、ある一時点における観察集団での疾病保有者の割合を意味する。生涯有病率とは、一生のうちに一度はその病気にかかる人の割合をいう。
2.× 各観察対象者の観察期間の総和は、主に罹患率を算出するときに使用される。
・罹患率とは、ある一定の観察期間に新規発生した患者数を、危険曝露人口一人ひとりの観察期間の総和(観察人年)で除したものである。疾病や死亡が生じることを事象の発生という。事象の発生は、ある一定期間を設定し、その期間内で新規に発生した頻度により把握できる。また、発生頻度の表現は、率(rate)の形で示される。
3~4.〇 正しい。観察期間に新たに発生した患者数/観察開始時点での観察対象集団の人数は、累積羅患率の計算に必要である。
・累積羅患率とは、ある年齢までにある病気と診断されるおおよその確率である。したがって、特定の期間中に新たに疾病が発生した人数を観察開始時点の集団の人数で割ったものといえる。
5.× 観察「終了」ではなく開始時点での観察対象集団の人数は、は、累積羅患率の計算に必要である(上の解説参照)。なぜなら、累積罹患率は、あくまで観察開始時点の集団を基準(分母)として、その後の新規発生割合を見る指標であるため。
38 調査について正しいのはどれか。2つ選べ。
1.患者調査は毎年実施される。
2.国勢調査で出生率が把握される。
3.社会生活基本調査は総務省が実施する。
4.人口動態調査は無作為抽出による標本調査である。
5.国民健康・栄養調査は健康増進法に基づいて実施される。
解答3・5
解説
目的:病院・診療所を利用する患者について、傷病状況の実態を明らかにする。
調査頻度:3年に1回、医療施設静態調査と同時期に実施している。
調査対象:標本調査(全国の病院、一般診療所、歯科診療所から層化無作為により抽出した医療施設の患者)
調査項目:患者の性別、出生年月日、住所、入院・外来の種別、受療の状況等。
調査方法:医療施設の管理者が記入。
(参考:「患者調査(基幹統計)」厚生労働省HPより)
1.× 患者調査は、「毎年」ではなく3年に1回実施される(※上参照)。
2.× 出生率が把握されるのは、「国勢調査」ではなく人口動態調査である。
・人口動態調査とは、出生、死亡、婚姻、離婚および死産の全数を対象とした悉皆調査(しっかいちょうさ)、全数調査である。それらの事象(人口動態事象)を把握する調査である。
・国勢調査とは、人口静態統計のもとになる調査で、日本に住んでいるすべての人を対象に5年に1回行う。国内の人口や世帯の実態を把握するために行われる。男女の別、出生の年月、就業状態、従業地または通学地、世帯員の数、住居の種類、住宅の建て方などを調べる調査である。
3.〇 正しい。社会生活基本調査は、総務省が実施する。
・社会生活基本調査とは、国(総務省)が実施する統計調査で、国民の生活時間の配分や余暇活動の実態などを把握するための重要な基幹統計調査である。睡眠、仕事、家事、学習、趣味、ボランティア活動などに人々がどれくらいの時間を費やしているかを調査し、ワークライフバランス施策などの基礎資料として活用される。
4.× 無作為抽出による標本調査であるのは、「人口動態調査」ではなく患者調査である。なぜなら、人口動態調査は、全数を対象とした悉皆調査(全数調査)であるため。悉皆調査とは、対象となるものを全て調べる調査の事である。
・標本調査とは、ある集団の中から一部の調査対象を選び出して調べ、その情報を基に、元の集団全体の状態を推計するものである。
5.〇 正しい。国民健康・栄養調査は、健康増進法に基づいて実施される。
・国民健康・栄養調査とは、国民健康・栄養調査とは、『健康増進法』に基づき、国民の健康状態や栄養摂取状況、生活習慣などを把握することを目的として、厚生労働省が毎年実施している標本調査である。この調査では、食生活の状況や身体計測、血液検査のほか、飲酒・喫煙・運動習慣などについても調べられる。得られたデータは、国や自治体が健康増進対策や生活習慣病の予防施策を立案・評価するための基礎資料として活用されており、国民の健康づくりにとって不可欠な調査である。
健康増進法は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、都道府県健康増進計画(義務)および市町村健康増進計画(努力義務)を策定する。平成14(2002)年に制定された。
【市町村が行う健康増進事業】
①健康手帳、②健康教育、③健康相談、④訪問指導、⑤総合的な保健推進事業、⑥歯周疾患検診、⑦骨粗鬆症検診、⑧肝炎ウイルス検診、⑨がん検診、⑩健康検査、⑪保健指導などである。
【都道府県の役割】
都道府県は、都道府県健康増進計画において、管内市町村が実施する健康増進事業に対する支援を行うことを明記する。都道府県保健所は、市町村が地域特性等を踏まえて健康増進事業を円滑かつ効果的に実施できるよう、必要な助言、技術的支援、連絡調整及び健康指標その他の保健医療情報の収集及び提供を行い、必要に応じ健康増進事業についての評価を行うことが望ましい。都道府県は、保健・医療・福祉の連携を図るとともに、市町村による健康増進事業と医療保険者による保健事業との効果的な連携を図るために、地域・職域連携推進協議会を活性化していくことが望ましい。
39 感染症発生動向調査で全数把握の対象となるのはどれか。2つ選べ。
1.結核
2.麻疹
3.手足口病
4.マイコプラズマ肺炎
5.性器クラミジア感染症
解答1・2
解説
感染症発生動向調査は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づく施策として位置づけられた調査で、感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の国民や医療機関への迅速な提供・公開により、感染症に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生及びまん延を防止することを目的としている。
【感染症発生動向調査による全数把握対象疾患】
全数把握対象疾患を診断したすべての医師が、患者の発生について届け出なければならない。
①新感染症の疑い
②新型インフルエンザ等感染症
③指定感染症
④1~4類までの全疾患と5類の一部疾患
定点把握対象疾患とは、5類感染症の定点把握対象疾患を指す。都道府県知事により指定された医療機関(指定届出機関)のみ、医療機関の管理者が患者の発生について届け出なければならない。主な疾患として、インフルエンザ(鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症を除く)、性器クラミジア感染症、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、その他の感染症(各省で指定)である。
(※参考:「感染症発生動向調査について」厚生労働省HPより)
1.〇 正しい。結核(2類感染症)は、感染症発生動向調査で全数把握の対象となる。
・肺結核とは、結核菌による感染症で、体の色々な臓器に起こることがあるが多くは肺のことである。結核菌は、喀痰の中に菌が出ている肺結核の患者と密閉空間で長時間(一般的には数週間以上)接触することにより空気感染でうつる。リンパ節結核や脊椎カリエス(骨の結核)など、肺に病気のない結核患者からはうつらない。また肺結核でも、治療がうまくいって喀痰の中に菌が出ていない患者さんからはうつることはない。また、たとえ感染しても、発病するのはそのうち1割ぐらいといわれており、残りの9割の人は生涯何ごともなく終わる。感染してからすぐに発病することもあるが、時には感染した後に体の免疫が働いていったん治癒し、その後数ヶ月から数十年を経て、免疫が弱ったときに再び結核菌が増えて発病することもある。結核の症状には、咳、痰、血痰、熱、息苦しさ、体のだるさなどがある。
2.〇 正しい。麻疹(5類感染症の一部疾患)は、感染症発生動向調査で全数把握の対象となる。なぜなら、麻疹は、感染症法において5類感染症に分類されているが、感染力が非常に強く、集団発生を起こしやすいことから、発生動向の把握や対策が重要視されているため。
・麻疹とは、麻疹ウイルスの感染後、10~12日間の潜伏期ののち発熱や咳などの症状で発症する病気のこと。38℃前後の発熱が2~4日間続き、倦怠感(小児では不機嫌)があり、上気道炎症状(咳、鼻みず、くしゃみなど)と結膜炎症状(結膜充血、目やに、光をまぶしく感じるなど)が現れて次第に強くなる。
3.× 手足口病(5類感染症)は、定点把握対象疾患である。
・手足口病とは、手のひらや足の裏、口の中などに小さな水ぶくれのような発疹ができるウイルス感染症である。原因はコクサッキーウイルスやエンテロウイルスといったウイルスへの感染である。5歳までの子どもがかかることが多く、夏に流行のピークを迎える。
4.× マイコプラズマ肺炎(5類感染症)は、定点把握対象疾患である。
・マイコプラズマ肺炎とは、「肺炎マイコプラズマ」という細菌に感染することによって起こる呼吸器感染症である。小児や若い人の肺炎の原因としては、比較的多いものの1つである。例年、患者として報告されるもののうち約80%は14歳以下であるが、成人の報告もみられる。
5.× 性器クラミジア感染症(5類感染症)は、定点把握対象疾患である。
・性器クラミジア感染症とは、単純ヘルペスウイルス(HSV)の感染によって性器やその周辺に水疱や潰瘍等の病変が形成される疾患である。感染症法下では4類感染症定点把握疾患に分類されている。感染機会があってから2〜21日後に外陰部の不快感、掻痒感等の前駆症状ののち、発熱、全身倦怠感、所属リンパ節の腫脹、強い疼痛等を伴って、多発性の浅い潰瘍や小水疱が急激に出現する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症予防法、感染症法、感染症新法)は、感染症の予防および感染症患者に対する医療に関する措置について定めた日本の法律である。平成10年(1998年)に制定された。主な内容は、①1~5類感染症の分類と定義、②情報の収集・公表、③感染症(結核を含む)への対応や処置。
【「感染症法」の対象となる感染症】
①1類感染症(7疾患:エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱・痘そう(天然痘) ・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱)
対応:原則入院・消毒等の対物措置(例外的に建物への措置,通行制限の措置も適用対象とする)
②2類感染症(6疾患:・急性灰白髄炎(ポリオ)・結核 ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群(SARS)・特定鳥インフルエンザ(H5N1, H7N9) ・中東呼吸器症候群(MERS))
対応:状況に応じて入院・消毒等の対物措置
③3類感染症(5疾患:・コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症(0157等)・腸チフス ・パラチフス)
対応:・特定職種への就業制限・消毒等の対物措置
④4類感染症(44疾患:※一部抜粋。・E型肝炎・A型肝炎 ・黄熱・Q熱・狂犬病・チクングニア熱・鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)・炭疽 ・ボツリヌス症 ・マラリア ・野兎病・重症熱性血小板減少症候群(SFTS)・デング熱・ジカウイルス感染症・日本脳炎・その他感染症(政令で指定))
対応:・感染症発生状況の情報収集、分析とその結果の公開,提供・媒介動物の輸入規制・消毒等の対物措置
⑤5類感染症(46疾患:※一部抜粋。・インフルエンザ(鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ等感染症を除く)・ウイルス性肝炎(E型・A型を除く)・クリプトスポリジウム症・後天性免疫不全症候群(AIDS)・性器クラミジア感染症 ・梅毒・麻疹・百日咳・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症・その他感染症(省令で指定))
対応:・感染症発生状況の情報収集、分析とその結果の公開情報提供
40 40歳以上の男性を対象とした疫学研究で、虚血性心疾患死亡率(10万人年対)を観察した虚血性心疾患死亡率は、喫煙群では50.0、非喫煙群では25.0であった。
このときの寄与危険割合を百分率で求めよ。
ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。
解答:①②%
①:0~9
②:0~9
解答50(%)
解説
人口寄与危険割合(集団寄与危険割合)とは、疫学における指標の1つであり、曝露群における疾病発生のうち、その曝露要因が寄与した(原因となった)部分がどれくらいの「割合」を占めるかを示す指標である。喫煙者の肺がん発生率が10%、非喫煙者が1%の場合、寄与危険割合は (10% – 1%)/ 10% = 90% となる。これは、喫煙者の肺がんリスクの90%が喫煙によるものだ、という意味合いになる。
したがって、人口(集団)寄与危険割合は、人口集団(曝露群+非曝露群)の疾病の発生率から非曝露群の発生率を引くことで曝露による増加分が占める割合を示す。
【人口(集団)寄与危険割合 =(人口集団の発生率一非曝露群の発生率)÷ 人口集団の発生率 × 100(%)】で表される。
寄与危険割合は、喫煙などの特定の因子が疾患の発生にどれだけ寄与しているかを示す指標である。
以下の公式で算出する。
寄与危険割合 = (喫煙群の虚血性心疾患死亡率 - 非喫煙群の虚血性心疾患死亡率)÷ 喫煙群の虚血性心疾患死亡率 × 100%
・喫煙群の虚血性心疾患死亡率:50.0
・非喫煙群の虚血性心疾患死亡率:25.0を代入。
寄与危険割合
=(50.0 - 25.0)÷ 50.0 × 100%
= 0.5 × 100%
= 50%
したがって、この疫学研究における寄与危険割合は50%である。
解答:①5、②0%
 希望の解説ブログ
希望の解説ブログ 

